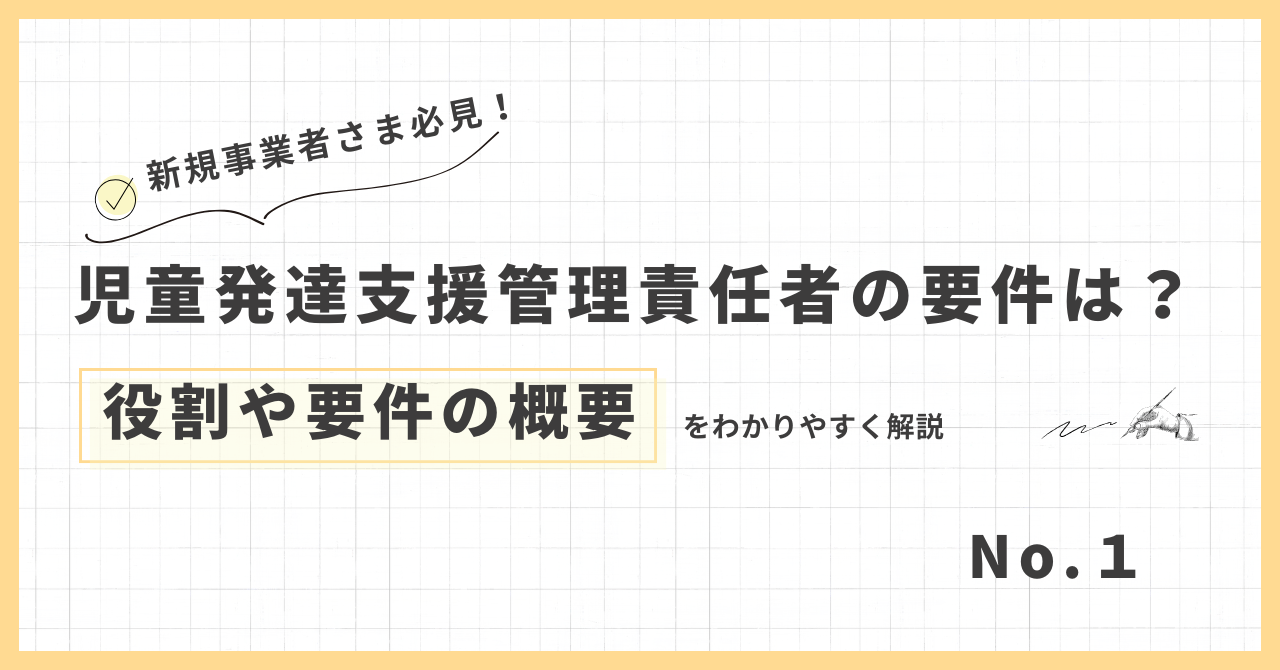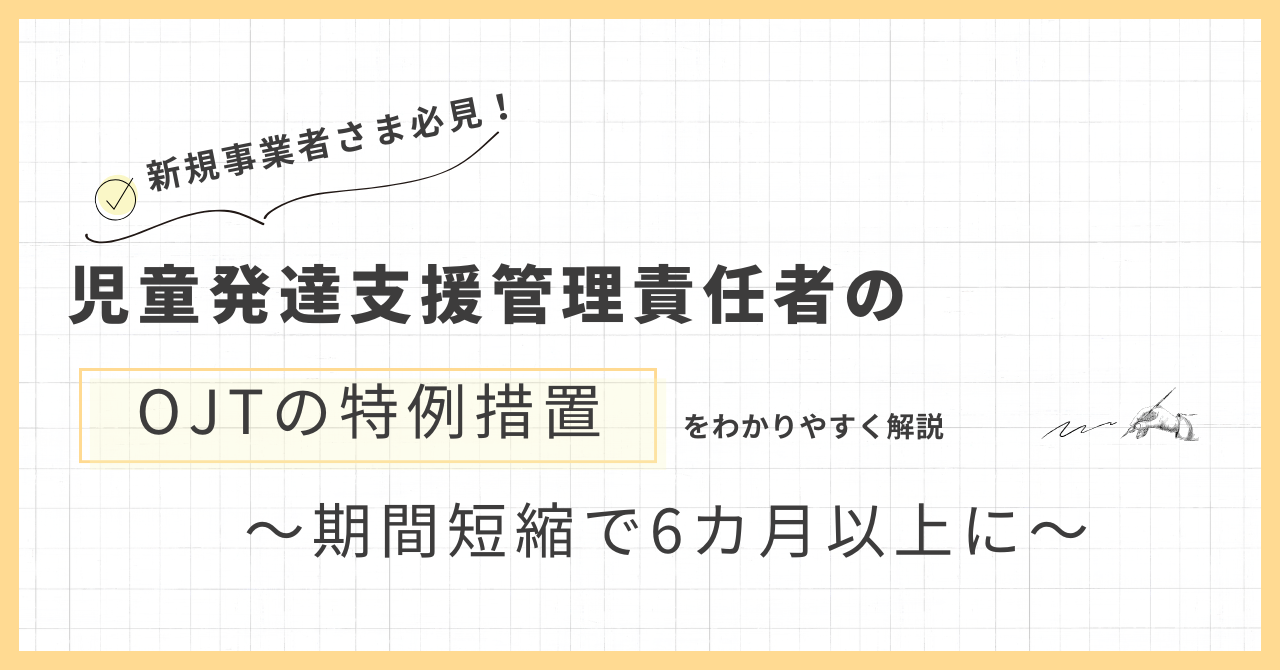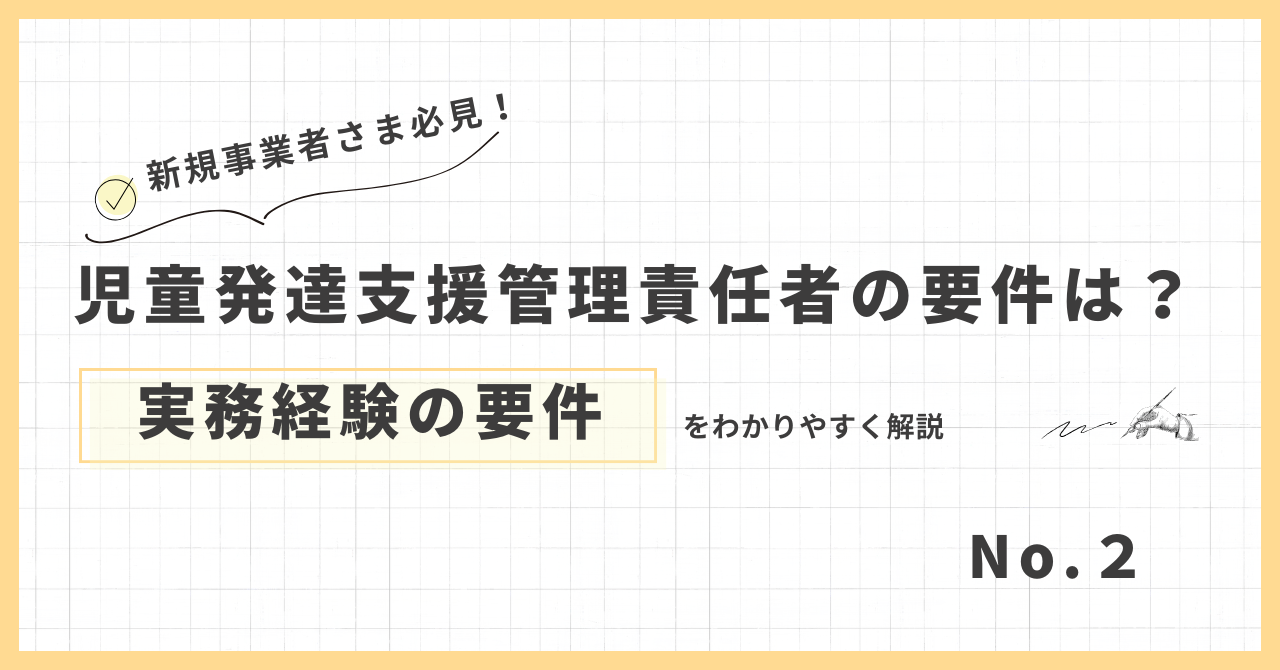障害児通所支援(放デイ・児発)の人員配置基準と役割をわかりやすく解説

放課後等デイサービスや児童発達支援などの指定を受けるためには、法人格・人・設備・運営などさまざまな要件を満たす必要があります。
今回は、その中でも「人(人員)」に関する要件を、わかりやすく解説します。
放課後等デイサービスや児童発達支援を始めるためには、次のような人員を配置する必要があります。
| 配置人数 | 備考 | |
| 管理者 | 1人以上 | ・支障がなければ、他の職務と兼務可 ・専門資格不要 |
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | 1人以上 | 1人以上は常勤かつ専任 |
| 児童指導員・保育士 | 2人以上 | 障害児の人数が10人までの場合 |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合 | |
| 看護職員 | 医療的ケアを行う場合 |
※重症心身障害児の受け入れを行う場合、人員の基準が異なります。
管理者
職員の管理や、運営方針の決定など、事業所全体のマネジメントを担います。
専門資格は不要で、支障がなければ他の職務との兼務も可能です。
児童発達支援管理責任(児発管)
事業所の現場責任者となる存在です。
実務経験や研修など、一定の要件を満たす必要があります。
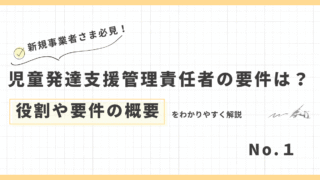
児童指導員・保育士
児発管が作成した個別支援計画書に基づき、実際に子どもへの支援を行います。
障害児の人数によって配置人数が変わり(基準:10人につき2人)、11~15人であれば3人以上、16~20人であれば4人以上の配置が必要です。
児童指導員になるには、児童指導任用資格が必要で、この資格は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条」に基づき定められています。
- 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者
- 社会福祉士の資格を有する者
- 精神保健福祉士の資格を有する者
- 大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者
- 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、大学への入学を認められた者、若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めた者
- 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めた者
機能訓練担当職員・看護職員
機能訓練を行う場合や医療的ケアを行う場合にそれぞれ配置する必要があります。
ただし、医療的ケアについては、医療機関と連携して看護職員が訪問する形をとる場合、事業所内に看護職員を配置しなくても認められる場合があります。
今回は、障害児通所支援(放デイ・児発)の「人(人員)」に関する要件をまとめました。
事業を始めるには、人員配置の基準を満たすことも大切なポイントです。
本記事では全国的に共通する基準をもとに整理しましたが、指定権者ごとに独自の基準や解釈が設けられている場合もあります。
そのため、詳しくは指定権者に確認されることをおすすめします。
ご不安な場合は、当事務所でも一緒に確認・サポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
参照:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト)
(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/568)児発管(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/243)児童指導員